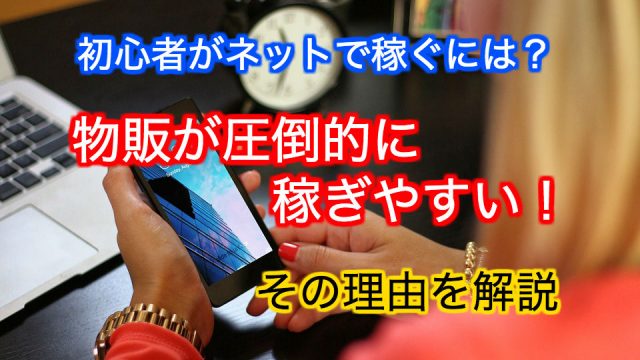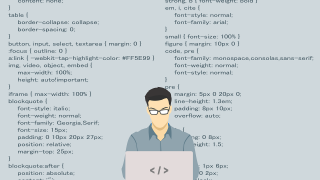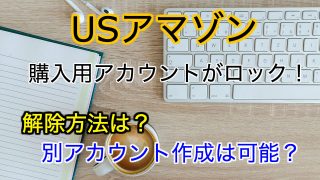前回の続きです。
今回の記事では、外注化を測って契約書を正式に交わす際に必要な項目を解説させていただきます。
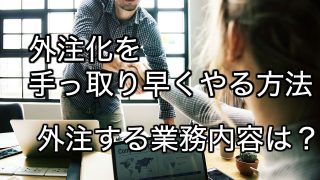
「契約書?なにそれ?」
って言う方にも契約書の大切さを伝えられたら良いなと思います。
目次
契約書の必要性
契約書と聞くと企業が取引先や雇用時に交わしていたりするイメージがありますよね。
皆さんに馴染みがある契約書といえば携帯電話を購入したりした際の契約書やアパートを借りる際の契約書などでしょうか?
これらの契約書って説明は受けるけどちゃんと聞かないで契約を結んでしまっていることがあると思います。
実はこれって有名企業とかならまだしも、一個人と契約する際にはかなり危険な行為です。
何故ならば、契約書というのは基本的に提示する側が有利になる様に作られているから。
当たり前といえば当たり前ですが、そこら辺の身の知れない個人と一緒に仕事をする際に、とんでもない条件になっていることも。
「じゃあ、そこら辺の人とは契約書なんて結ばなければいいじゃない。」
という意見もあると思いますが、それは違います。
”契約”という言葉は読んで字の通り”約束を契る”という意味です。
仕事において決まりや約束は必要ですよね。
契約書がない状態で業務をスタートしてしまうと、何かトラブルが発生した時にどちらがどの様な形で責任を取るのかの確認ができません。
なので、外注さんを迎え入れる際には必ず契約書を交わしましょう。
転売・せどりの外注化に必要な契約書の内容
転売やせどりで小売を営む方々は外注化する際にその業務内容によって必要な内容は異なってくると思います。
ここでは僕自身が最低限必要だと考えている契約内容を記載させていただきます。
業務内容の目的
当たり前ですが、どの様な業務内容を遂行するかを外注さんと話し合った上で決定し、契約書に記載する必要があります。
業務の履行
業務内容をきちんと遂行してもらうために、積極的に契約業務を行うという内容が必要です。
また、お互いの信用を傷つける行為やお互いのサービス・商品に対する信頼を傷つける背信行為は行わないという内容も欲しいですね。
資料や情報の提供
外注さんに業務内容を説明する際に必要となる資料や情報の提示は積極的に行うという内容があるといいでしょう。
逆のパターンで、外注さんの方で収集したデータや情報の提示も業務内容によっては記載した方がいいでしょう。(リサーチなどのデータ収集作業)
業務進行状況の報告
業務がどの程度進んでいるのか、どこまで完了したのかの報告を必ず行ってもらう様にしましょう。
報酬について
業務の報酬金額についてです。
時給換算なのか、成果型なのかをここで話し合って決めておきましょう。
損害賠償
商品を壊してしまった際にどちらがどの様に責任を負うのかとか。
外注さんを突然切り離した際に発生する賠償金の記載も行うことで外注さんも安心です。
契約期間と契約解除
契約はいつまで行うのか、契約解除するための条件など。
問題が発生した際の裁判所の管轄
万が一大きな問題が発生して裁判を行う必要が出てきた時のために、事前にどこの裁判所を利用するかを定めておきましょう。
NDA(秘密保持契約)も結びましょう
NDAは自社の内部情報を守るために必須です。
外注さんと契約が終わった後にその外注さんが別の同業者に情報提供をしていたら嫌ですよね。
それを防ぐ役割を担うのがNDAです。
こちらは契約書と同等のボリュームになるので、通常の契約書とは別に作成しましょう。
NDAには下記の内容を記載するといいでしょう。
秘密保持の内容
せどり・転売を行っている場合であれば
・仕入れ元
・販売先
・販売ノウハウ
・物流ノウハウ
などでしょうか。
これらの情報は他者に知れ渡っては困る情報ですので、細かく詰めていきましょう。
情報漏洩があった場合の損害賠償
万が一情報漏洩があった場合にどの程度の賠償を行うのかを定めましょう。
秘密保持の調査権限
秘密保持がされているかどうかの調査を行う権限があるという内容を記載しましょう。
問題が発生した際の裁判所の管轄
契約書と同様です。
契約書の内容はしっかり相手と相談の上決定する
契約書は自社を守るためのものではありますが、相手も守るためのものでもあります。
一方的にこちらが理不尽に有利な内容で契約しても相手はいい気がしないですし、こっちのために仕事を請け負ってもらうのに失礼ですよね。
つまり、外注として契約する以上は相手もプロだということです。
大袈裟に言うと、一緒に一つの事業を完成させるために協力するのですから、条件はお互いにフェアな方がいいでしょう。
お互いに気持ちよく仕事が出来るための環境を作るために契約内容はあるのです。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
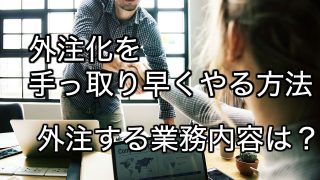
ーーーーーーーーーーーーーーー
僕は大学3年生の時に初めて自営業という道も選択肢にあるんだということを当時読んでいた本から学びました。
それから死に物狂いで勉強と実践を重ねて約半年後の大学4年生の春に法人設立まで至りました。
大学生で会社を経営している方ってたまにテレビの番組だったりネットニュースに流れてきますが
「才能があったからできたんでしょ?」という声も少なくありません。
しかし、僕自身はこれといって起業センスに長けていてお金儲けが得意だったというわけではありません。
事実、通っていた大学は名前を出すのも躊躇うほどのレベルの低さ。そして、ビジネスについて勉強を始めるまではお小遣いとアルバイト以外で何かを売って人からお金を頂くという経験をしたことがなかったのです。
そんな僕でも学びに対して目を背けずに立ち向かうことで、結果的に法人を設立してお金を稼ぐことができるようになりました。
ここに至るまでのプロセスは才能ではなく「努力」と「慣れ」がもたらしているものです。
「会社を設立する」なんてことは今の時代誰でもできますし、大事なのは会社を作ってからです。
法人設立後も気を緩めずに自分と向き合っていくことで稼ぎ続けることができ、そのチャンスは誰にだってあるのです。
僕が、この世界に足を踏み入れ、たくさんの学びを得て、会社を作るまでの過程とその理由を下記の記事では公開しています。
このブログを読んでくださっている方は「お金を稼ぎたい!」「経営について学びたい!」と考えている方がほとんどだと思います。
そんな方の参考に少しでもなれば嬉しいです。
ーーーーーーーーーーーーーーー
PS
物販ビジネスなどのクローズドな情報や、経営についてあまり全体公開できないような内容を下記のLINEマガジンにて無料で発行しています。
ご興味があれば登録してみてくださいね。